(大学への数学2004年3月号原稿)
(25字×45行 8頁)
英語多読のすすめ
古川 昭夫
大数読者の皆さん、こんにちは。今年度「対話で学ぶ数学」を担当していた古川です。私は、普段高校生には数学を教えているのですが、大学生や社会人には英語の学び方を教えています。今月は、この4月から大学生になる皆さんに新しい英語の学び方を紹介したいと思います。
1 個人的動機
私は中1から高1まで、有名な英語専門塾に通い、駿台模試にも英語で名前を載せたこともあったので、学生時代には英語への苦手意識は全くありませんでした。しかし、大学院時代、何本か英語で論文を書いて、外国の学会で発表する機会があったとき、自分にいかに英語力がないかということを痛感することになりました。 とはいうものの、大学院時代は、研究と塾のアルバイトで忙しく、英語にかける時間も無く、SEGの経営と授業に専念するようになってからは、それほど英語を使う必要性もなく英語への関心も薄れていきました。
しかし、SEGが数学教育界の中で一定の地位を占めることになると、諸外国から数学の先生や教育関係者がSEGに見学に来るような機会も増えてきます。また、SEGでも外国人の英語教師を採用するようになり、仕事の上でもそれなりに英語を使う必要がでてきました。
そんなある時、アメリカのオハイオで開かれたTeachers Teaching with Technology という数学教師の会議にTexus Instruments 社の招待で出席することになりました。この会議に出席した参加者は、急遽、短いスピーチを英語で行うことになりました。ところが、私を含めて日本人の数学教師はみんな英語がおそろしく下手で、あるスウエーデン人の数学教師に「私はみなさんにわかる英語を話しますから安心して下さい」と皮肉を言われるほどだったのです。
会議に出席した日本人数学教師は、数学の能力的には高かったにもかかわらず、このように馬鹿にされたことに対して憤慨すると同時に、こういうときに英語で抗議できない自分の英語力の無さを非常に情けなく思いました。
何で多くの日本人はこんなに英語の運用能力が低いのだろう。そのために日本人は国際会議で損をしているなぁ。今後はこんな風に言われないように英語を勉強しなおさなきゃいけないなあ。それに、これからの若い人達がこんな目に遭わないように、新しい英語教育を考えなければ・・・と心に誓ったのを今でも覚えています。
2 酒井さんとの出会い
大学受験のときに、文法の問題集は何冊もやったし、単語集や熟語集もそれなりに覚えたことがあるので問題集をやったり単語集を覚えたりしても実用的な英語能力は身に付かないということだけはその時点ですでに確信がありました。じゃあ、どうすればいいんだろうと思って、英語教育の本を何十冊と読みあさり、いろいろな英語教師対象の研究会にもでてみました。その中で、「どうして英語が使えない」(酒井邦秀著 筑摩書房)の「英語が使えないのは、学校英語が人工英語であり本当の英語からかけ離れているから」という主張が一番心に残りました。まさに自分の経験と一致したからです。早速直接意見を交換しました。大いに共感するところがあったとはいうものの、酒井さんは大学生を中心に教えていることもあり、中高校生にも通用する方法はまだ特に考えていないとのことでした。そこで、酒井さんにSEGで英語の実験クラスを担当してもらい、新しい英語教育法をともに考えていこうということになったのです。そして、最初の出会いから8年たった2001年の夏、多読による英語学習法をを広めるために、SSS英語学習法研究会を酒井さんと共に設立することにしました。
3 精読から多読へ
日本人は、英語の読み書きはできるが、聞く・話すは苦手であるとよく言われます。しかし、それは事実に反しています。ほとんどの大学生は英米の小学1~3年生の児童書が読めない・英米人に通じる英語の手紙が書けないというのが現実です。私達が英語を聞く・話す能力をつけるためには、まず、もっと読む・書く力を伸ばすべきなのです。
しかし、どうして、日本人は、学校や塾で中高6年間に2000時間以上の時間を英語の勉強に費やしているのに、大学生になっても40頁くらいの児童小説さえすらすらと読めないのでしょうか? それは、生の英語に触れる量が少なすぎたからだとしか思えません。
よく思い出してみれば、中学・高校の英語の授業時間は、ほとんど日本語の解説を聞いているだけでした。中高6年間で触れる英語の量はせいぜい10万語位です。しかも、その中には、英語として全く不自然であり英語とはいえないものが混じっています。10万語といえば、厚い文庫本一冊位の分量に過ぎません。 日本語の場合で想像してみて下さい。文庫を1冊読んだだけで、日本語の能力がつくと思えますか?
右下の写真の本は、The Zack Files というシリーズで、アメリカの小学校1年生~3年生対象の本です。1冊約4000語位の量
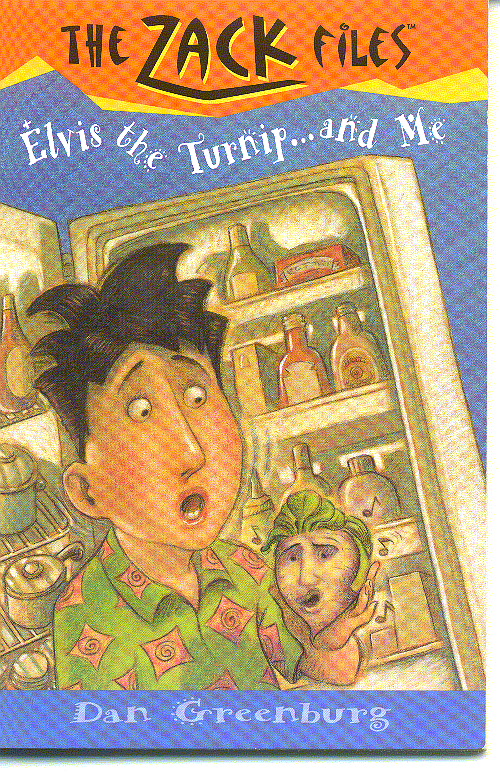
です。従って、この本を楽しむには、約4000語の英文を20分から40分で読む必要があります。(一冊の単行本のマンガを1時間もかけて読んでいたらたいてい楽しめないでしょう。それと同じでこの程度の本を何時間もかけていたのでは内容を楽しむことはできません) しかし、高校や予備校の授業で取り扱う英文はこの本と比べても非常に短いものです。例えば、京都大学の英語の1番・2番の英文はおのおの約400語くらいの量にすぎません。この400語くらいの文章を理解するのに、1時間程度の予習が要求され、授業で1時間程度かけて読むのが通例ですから、2時間でわずか400語の英語にしか触れられないのです。
普段の英語への接し方がこんなペースですから、小学生用の本だといっても4000語もある本となると、1冊読むのに10時間はかかる計算となり、とても読んで楽しむというわけにはいかなくなってしまうのです。
短くて難しい文を精密に読む(これを精読といいいます)ことを繰り返していけば、長くて難しいものが読めるようになるというのが、今までの英語教育の考え方でした。しかし、その結果は、やさしくて長いものさえ読めない人の大量発生でした。
短くて難しい英文を辞書を引いて一文一文を分析しながら精読するのではなく、長くて易しい英文を辞書を引かずに英語の語順のまま理解して読むことにより、長くて難しいものも読めるようになるというのが私達が薦めている新しい英語学習法です。
細かいことを気にせず、わからない部分は適当に飛ばして読むことを多読といいいます。精読から多読に切り替えれば、学生なら年間100万語~300万語の英語に触れることができます。このように大量の英語に触れることによって大量の英語が脳にたまり、英語で考えることが自然にできるようになり、特別な訓練なしに、自然に口から英文が出てくるようになるのです。
4 夏目漱石も薦めていた多読法
英語ができるようになるには、英語をたくさん読むことが最前の方法であるということは、今までも多くの人がいっています。例えば、夏目漱石は明治39年『現代読書法』にて、つぎのように述べています。
「英語を修むる青年はある程度まで修めたら辞書を引かないで無茶苦茶に英書を沢山読むがよい、少し解らない節があって其処は飛ばして読んでいってもドシドシと読書していくと終いには解るようになる、又前後の関係でも了解せられる、其れでも解らないのは滅多に出ない文字である、要するに英語を学ぶ者は日本人がちょうど国語を学ぶような状態に自然的習慣によってやるがよい、即ち幾変となく繰り返し繰り返しするがよい、ちと極端な話のようだが之も自然の方法であるから手当たり次第読んでいくがよかろう。彼の難句集なども読んで器械的に暗唱するのは拙い、殊に彼のようなものの中から試験問題等出すというのはいよいよつまらない話である、何故ならば難句集などでは一般の学力を鑑定することは出来ない、学生の綱渡りが出来るか否やを視るぐらいなもので、学生も要するにきわどい綱渡りはできても地面の上が歩けなくては仕方のない話ではないか、難句集というものは一方に偏していわば軽業の稽古である。試験官などが時間の節約上且つは気の利いたものを出したいというのであんな者を出すのは、ややもすると弊害を起こすのであるから斯様なもののみ出すのは宜しくない。」
しかし、実際に今まで英語の教師が生徒に勧める多読用の本というのは普通の学生には難しすぎる本ばかりだったので、多読はかなり英語ができる人を対象とした方法と思われていました。それを抜本的に見直し、非常に易しい絵本からはじめることにより、普通の人にも実行可能にしたのが、SSS式多読法です。
5 SSS式多読法
それでは、私達が提唱しているSSS式多読法では具体的にどんな本を使って多読をするのかを簡単に紹介しましょう。
多読に使う本としては、次の3種類があります。
1 学習者向けのGraded Readers
2 英米の児童向けのGraded Readers
3 英米の児童向けの一般書(児童書)
1は、英語を外国語として学ぶ人のために、語彙や文法を制限してレベル別に作られた本で、主なものとして、Penguin Readers, Oxford Bookworms, Macmillan Guided Readers, Cambidge English Readers の4種類があります。例えば、Penguin Readers は、7段階のレベル別読み物で構成されています。いちばん易しいPenguin Easystarts は、その内容は、下図のような感じの本で、基本200語で書かれた総語数900語程度の本です。、
一番難しいPenguin Level 6の本は、、基本3000語で書かれた総語数30000語程度の次の様な本です。
後者は、DNAの2重螺旋構造を発見したワトソンの同名の本を短く書き直したものですが、原著の雰囲気を十分に味わえます。英語学習者向けのGraded Readers といわれるこのタイプの本は、オリジナルな小説・映画の原作を書き直したもの・古典小説を書き直したものがメインですが、nonfictionのシリーズもあります。
2の英米の児童向けのGraded Readers は、英米の幼児~小学生用の絵本です。イギリスの小学校の副読本としても使われているOxford Reading Tree や、アメリカで良く読まれている I Can Read Books シリーズや、Step into Reading シリーズなどがあります。英米の子供向けに書かれているので、使われている単語も学校英語にはないものもたくさんでてきますが、絵本なので挿し絵で本のストーリーが想像でき、日本人の学習者にも非常に人気があります。
Oxford Reading Tree は、日本では、stage1 からstage9までのものが売られています。stage3 というと次のような1頁に約1行しかない非常に簡単な絵本です。 す
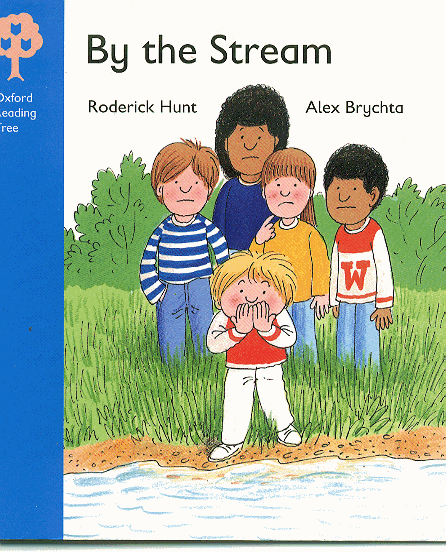
でに、rug なんて単語がで
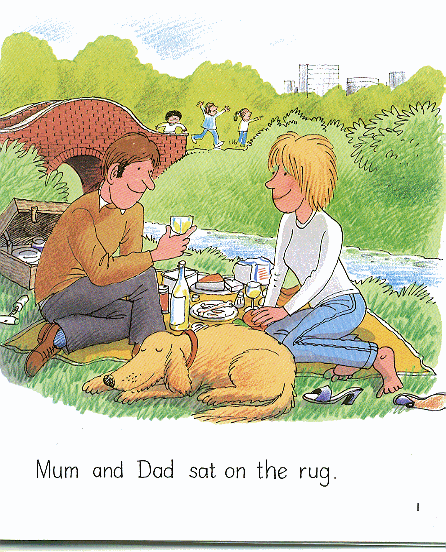
てきていて受験生の中にもこの単語を知らない方もいるかと思いますが、絵が大きな助けになるのでその意味は絵からたいていの場合想
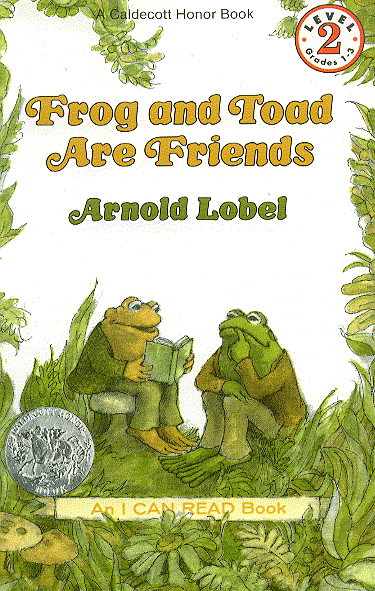
像がつきます。
I Can Read Books シリーズはほのぼのとした内容が多い絵本で、中でも、Lobel の Frog & Toad のシリーズは、中学生から大人まで幅広い人気があります。みなさんの中にも、昔、日本語でよんだことのある人も多いのではないでしょうか?
3の英米の普通の児童書は、Harry Potter シリーズに代表される本格的な児童小説です。英米でも日本同様児童書は非常に数多く出版されており、SSS英語学習法研究会では、会員が実際にそれを読んで総語数・難易度・面白さを調査しています。調査というと堅苦しい感じですが、実際には30代~40代を中心とする大人達が調査や英語の学習の美名の下に、児童小説を読んで楽しんで。感想を交換しあって盛り上がっています。これらのうちで、最近、、非常に人気がある作品をいくつか紹介します。
The Zack Files Series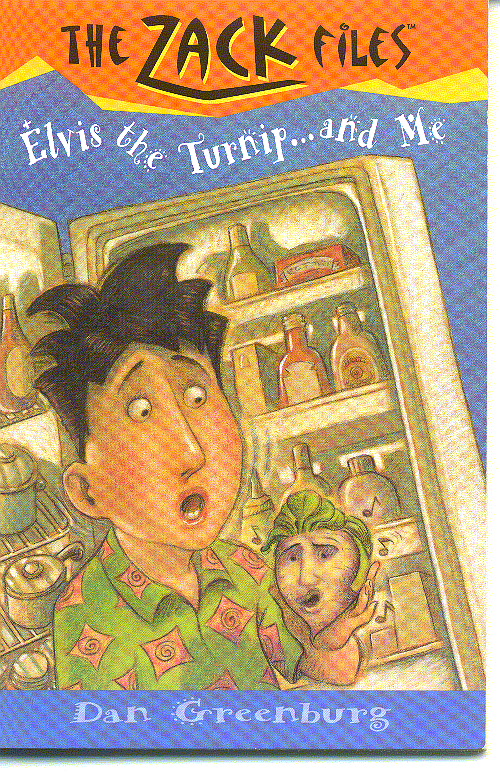
10歳6ケ月の主人公Zackの身の回りでは、UFOが現れたり、Elvis Presley そっくりの蕪(かぶ)が現れたり怪事件が続出します。でも、父親はどんな怪事件にも動転せず、息子の言葉を信じて一緒に問題解決にあたるというパターンの物語です。奇想天外な状況のに親子の関係は妙に現実的でそのアンバランスが対照的な傑作です。
Marvin Redpost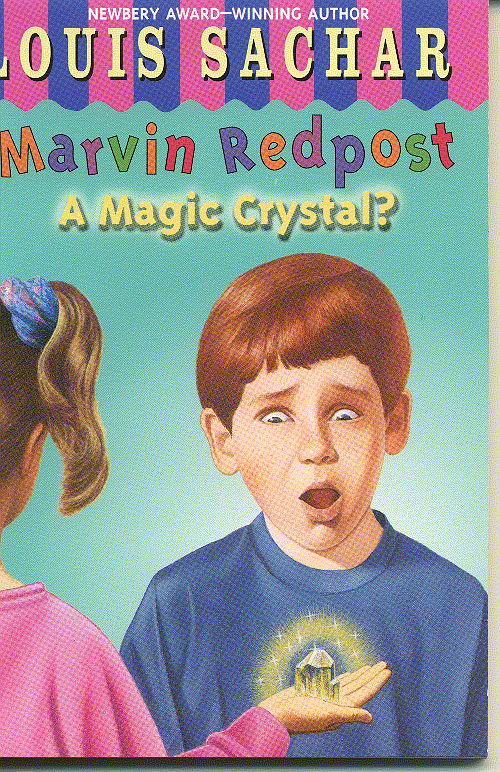
映画にもなったHolesでアメリカの児童文学賞をとったLouis Sacher の作品です。小学生のMarvinの同級生の男友達・女友達の微妙な心理を非常にうまく描いています。鼻くそをほじくっているところを目撃されて窮地に陥るMarvinの話は中でも傑作です。
7 SSSの多読3原則
多読を楽しく続けるために守るべきことは非常に簡単です。これを私達は多読3原則といっています。
1 本を読むときに、辞書は引かない
辞書を引く最大の欠点は読書のリズムを崩すということです。みんな、子供の頃、本を読むのに辞書を引きながら読んだことはなかったはずです。SSSでは、幼児が日本語を学ぶように英語を学ぶのが大原則です。
2 分からないところがあったら、飛ばす
辞書を引かないので、当然わからない単語が出てきます。そういうところは適当に想像してどんどん飛ばしていきましょう。多少飛ばしても、十分ストリーを楽しめるように本はできているのです。
3 つまらなくなったらその本はやめる
ストーリーが分からなくなったり、わかっても内容が楽しめないときはすっぱりその本を読むのをやめて別の本に移るのがいいのです。この多読3原則を守れば誰でも英語での多読を続けることができます。一緒に楽しむ友達がいればなおいいでしょう。
8 辞書をひかなくて意味は分かるのか?
多読3原則を説明すると、辞書を使わなかったら永久に意味が分からないのではないかという疑問をもたれる方も多いでしょう。でも、心配することはありません。重要な表現は何度でもでてくるので、その前後の状況から必ず意味がわかるようになるのです。たとえば、
What are you waiting for? という英文を例にとって説明しましょう。
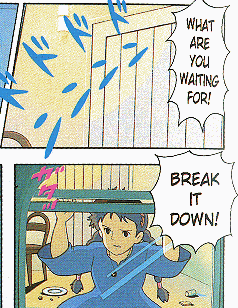
この英文を訳せといわれたら、多くの人が "あなたは何を待っているのですか?”と訳すでしょう。でも、それはどんな時に使われる表現なのか?その真の意味は何なのかは、一語一語を辞書を引いても決してわかりません。しかし、この表現はかなりよくでてくる表現で、たとえば、天空の城ラピュタの右上のシーンやピーチガールの次の様なシーンから、
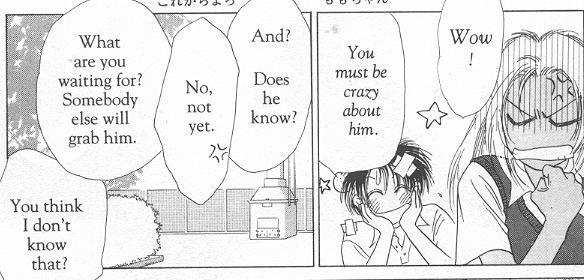
「何ぐずぐずしているの?」っていうのが真の意味だってことは自然に状況からわかるのです。
もっと詳しいことを知りたい方は、ぜひ、「今日から読みます英語100万語」(日本実業出版・古川昭夫・河手真理子著 1400円)を買って読んでみてください。具体的な洋書の入手法も含めて、多読を進めるための様々な情報を紹介しています。
(ふるかわあきお・SSS英語学習法研究会
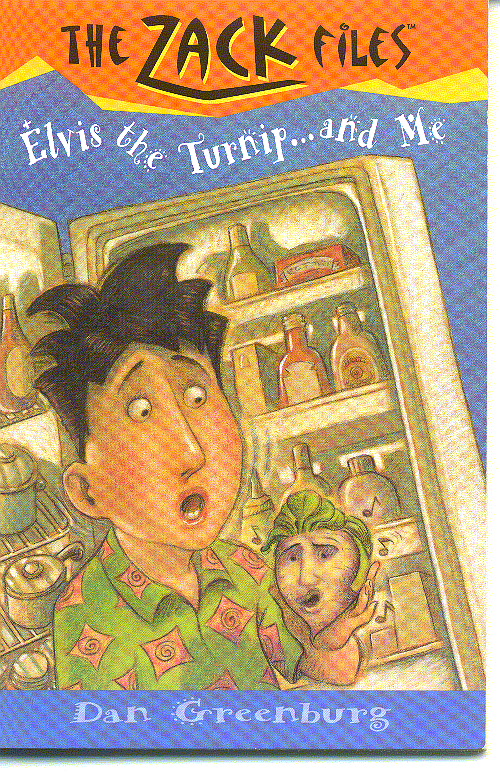 です。従って、この本を楽しむには、約4000語の英文を20分から40分で読む必要があります。(一冊の単行本のマンガを1時間もかけて読んでいたらたいてい楽しめないでしょう。それと同じでこの程度の本を何時間もかけていたのでは内容を楽しむことはできません) しかし、高校や予備校の授業で取り扱う英文はこの本と比べても非常に短いものです。例えば、京都大学の英語の1番・2番の英文はおのおの約400語くらいの量にすぎません。この400語くらいの文章を理解するのに、1時間程度の予習が要求され、授業で1時間程度かけて読むのが通例ですから、2時間でわずか400語の英語にしか触れられないのです。
です。従って、この本を楽しむには、約4000語の英文を20分から40分で読む必要があります。(一冊の単行本のマンガを1時間もかけて読んでいたらたいてい楽しめないでしょう。それと同じでこの程度の本を何時間もかけていたのでは内容を楽しむことはできません) しかし、高校や予備校の授業で取り扱う英文はこの本と比べても非常に短いものです。例えば、京都大学の英語の1番・2番の英文はおのおの約400語くらいの量にすぎません。この400語くらいの文章を理解するのに、1時間程度の予習が要求され、授業で1時間程度かけて読むのが通例ですから、2時間でわずか400語の英語にしか触れられないのです。
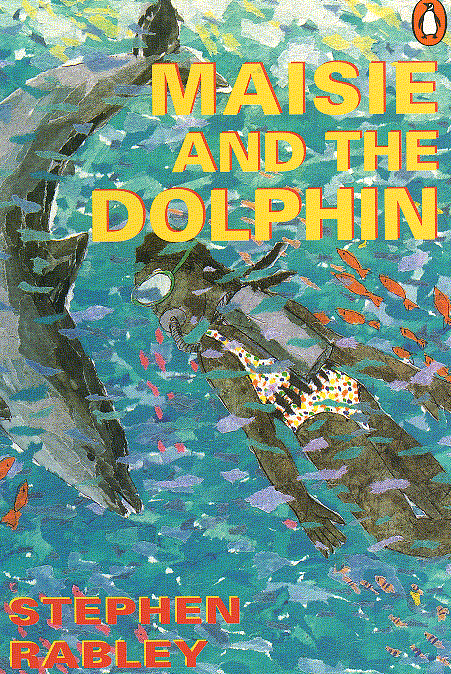
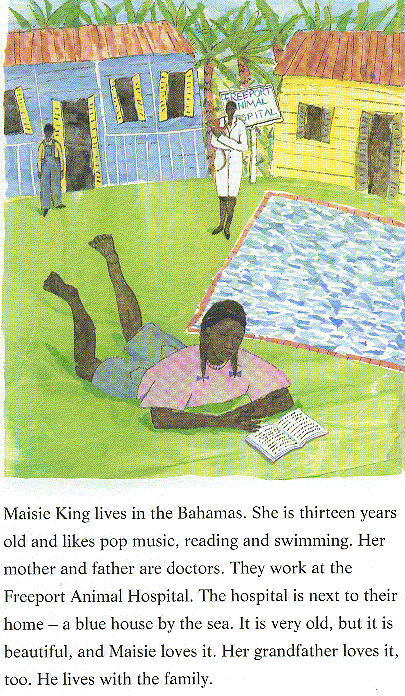
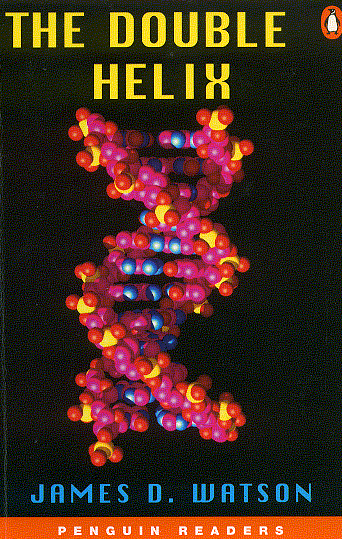
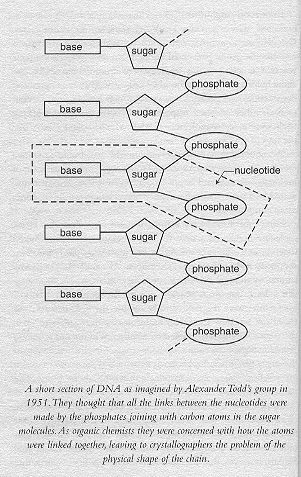
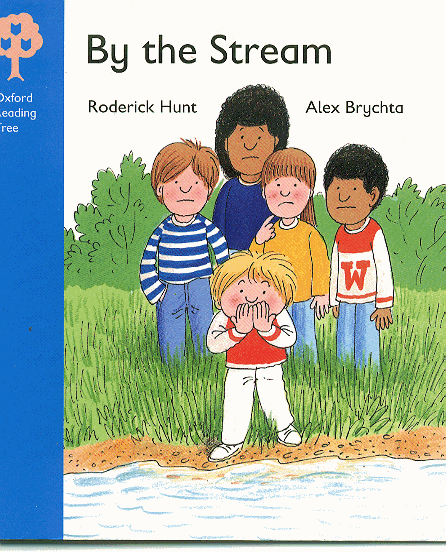 でに、rug なんて単語がで
でに、rug なんて単語がで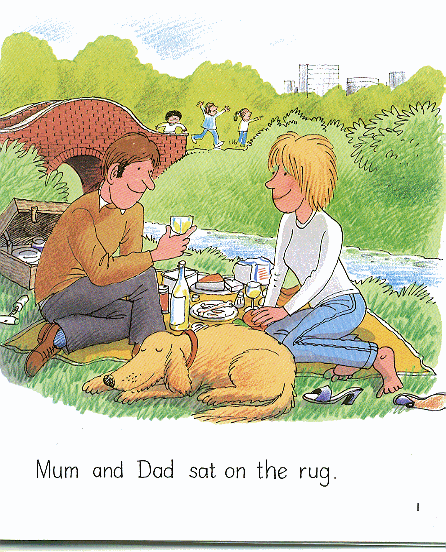 てきていて受験生の中にもこの単語を知らない方もいるかと思いますが、絵が大きな助けになるのでその意味は絵からたいていの場合想
てきていて受験生の中にもこの単語を知らない方もいるかと思いますが、絵が大きな助けになるのでその意味は絵からたいていの場合想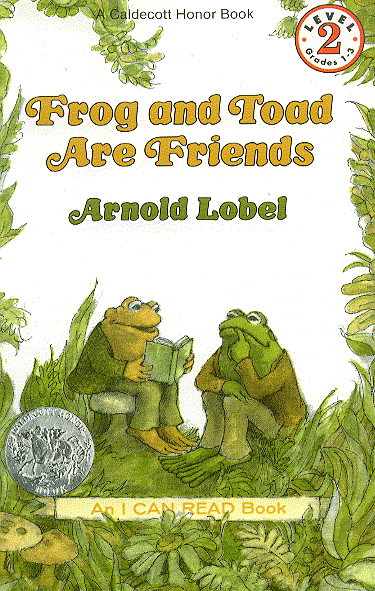 像がつきます。
像がつきます。
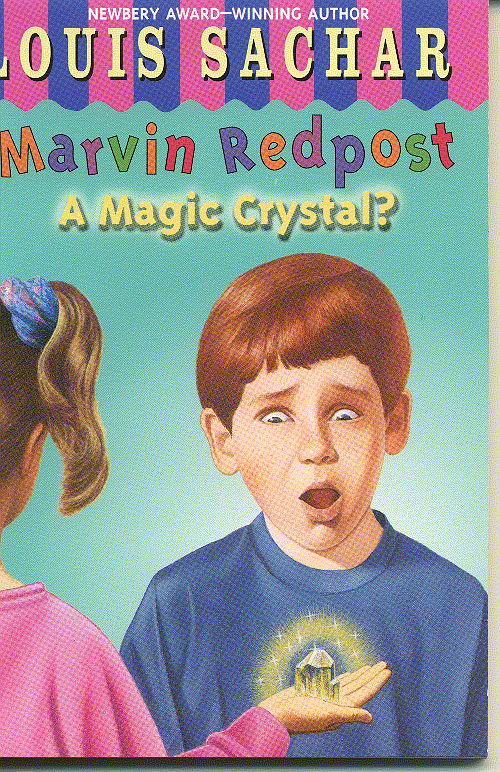
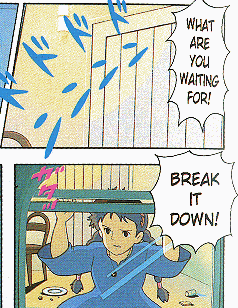 この英文を訳せといわれたら、多くの人が "あなたは何を待っているのですか?”と訳すでしょう。でも、それはどんな時に使われる表現なのか?その真の意味は何なのかは、一語一語を辞書を引いても決してわかりません。しかし、この表現はかなりよくでてくる表現で、たとえば、天空の城ラピュタの右上のシーンやピーチガールの次の様なシーンから、
この英文を訳せといわれたら、多くの人が "あなたは何を待っているのですか?”と訳すでしょう。でも、それはどんな時に使われる表現なのか?その真の意味は何なのかは、一語一語を辞書を引いても決してわかりません。しかし、この表現はかなりよくでてくる表現で、たとえば、天空の城ラピュタの右上のシーンやピーチガールの次の様なシーンから、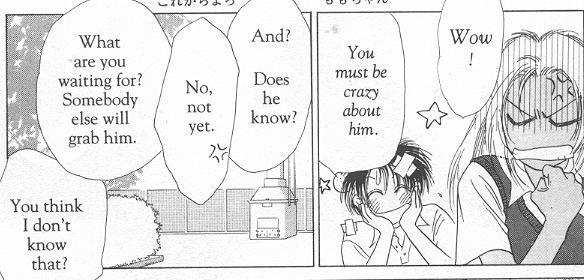 「何ぐずぐずしているの?」っていうのが真の意味だってことは自然に状況からわかるのです。
「何ぐずぐずしているの?」っていうのが真の意味だってことは自然に状況からわかるのです。